こんにちは、「おやじサーファーの生き方戦略」です。
万年初心者なのに気持ちは常にトッププロ。そんな僕のサーフィン履歴を少しずつ振り返っていこうと思います。
初めての方にも「こいつ、こんな感じで始めたのか」と知ってもらえたらうれしいです。
というわけで今回は――チーマー風の男に誘われて海に行ったら、ボッコボコにされた話です。
スノボ男子、サーフィンと出会う
大学時代、僕はスノボにドハマりしていた。
冬になれば、雪山へ。
ハーフパイプに入っては「オレ、イケてる感」を全力で出していた。
あの頃は「上手くなればモテる」という幻想が、僕の全てを突き動かしていた気がする。
就職してからもその勢いは止まらず、新卒で入った会社でもスノボ好きな同僚たちに囲まれ、自然と冬になると連れ立って雪山へ行く日々が続いた。
そんな仲間の中に、ちょっと異質な存在がいた。
チーマー風な友人「T崎」 、登場
遊び仲間 T崎。
東京出身。
ロン毛。
色黒(サーファーだから)。
渋谷のチーマー風。
……って、「チーマー」って今の若い人に通じるんかな?
たぶん令和の高校生が聞いたら「チーマ? 何味ですか?」とか言いそう。
でも僕らの時代はそれが最先端のカッコよさだったのだ。そう、あの渋谷センター街で肩で風切って歩くような存在。
T崎はそんな“ザ・渋谷系”の空気をまとっていた。
で、なぜかちょっとだけサッカーの北澤っぽかった。本人もそれをわかってて、髪型とか意識してた節がある。
突然の誘い、そして海へ
そんなある日、T崎が急に言った。
T崎:「明日、海行くわ。波、上がってんだよね」
僕:「海…?あの、サーフィンってやつ?」
T崎:「そう、サ〜フィン♪」
なんかムカつくノリだったけど、僕は思った。
「サーフィンか…。でも、スノボできるし、似たようなもんだろ」
そして、何を血迷ったか、思いきってこう言ってしまった。
「俺も行ってみたい。連れてってよ」
T崎はノリノリで了承。板とウエットはT崎の貸し出し。
後から思えば、その板は初心者向きではまったくなかった。ただただ細くて不安定。だけど、当時はそんなこと知る由もない。
初めての海は、想像の10倍しんどかった
そして、迎えた初サーフィン当日。
5月とはいえ、まだ水は冷たい。
寒いし、ウエットもパツパツだし、テンションも謎に上がってこない。
「これはもしかして…早く帰りたいかもしれん」と思ったのは、入水から10分後だった。
スノボ経験者として、最初はイケると思ってた。
「まぁ、板に乗るスポーツでしょ? 余裕やん」と。
ところがどっこい。
サーフィンは、パドリングという悪魔の儀式から始まる。
パドルしても進まない。
板は不安定。
T崎は全然教えてくれない。
「波、見て自分でタイミング掴んで!」とか言われても、こっちは波どころか水しぶきで、自分の鼻先も見えてない。
当然、立てるわけもなく、ただただ波に転がされ、全身ダルダルになって浜に戻る。
それでも、また来たくなる。モテたいから。
正直、海から上がった時はこう思ってた。
「いやもう、しんどいわ…帰りたい……」
体はバキバキ、寒い、全然立てない、T崎には全然教えてもらえん。
波どころか、ボードの上に座ることすらできなかった。
心は完全に折れていた。
なのに――
着替え終えて、潮風の中でT崎と缶コーヒーを飲みながら海を見ていると、
さっきまでの疲れがスーッと引いていった。
そして、なぜか心の奥でスイッチが入った。
「…モテてぇ……」
冷静に考えるとめっちゃ情けないけど、
あの海でキラキラしてたT崎の姿が、ずっと頭から離れなかった。
ロン毛、色黒、口数少なめで、波に乗る姿がいちいちサマになる。
そしてなにより、渋谷のチーマー風。
いや、「渋谷の」って言ったけど、あいつ多摩在住やねん。
駅で言うと「聖蹟桜ヶ丘」とかそのへん。
渋谷まで電車で1時間コース。
なのに、なぜか渋谷の風をまとっていた。理不尽。
でも、そんなT崎のサーフィン姿を見て思った。
「このまま“田舎者、初日で心折れる”じゃ終われん!」
「絶対うまくなって、俺もモテてやる!!」
そんな誓いを立てた、20代後半の初夏。
九州から出てきた田舎者が、波に揉まれ、心を打ち砕かれながらも、
サーフィンという新しい世界へのドアを、自ら開けた瞬間だった。
理由はシンプル。
「モテたいから」――ただそれだけ。
▶️ 次回の記事:サーフィン履歴その2:ロングボードとの出会い編 〜初心者がショートで挫折した話〜
▶️ 全シリーズ一覧はこちら
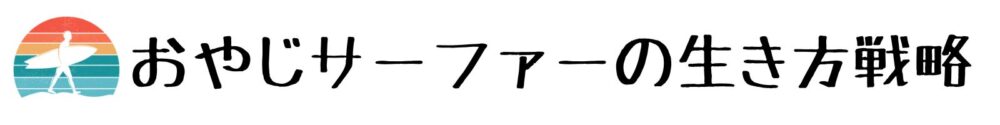



コメント